原点の夢に戻るために多くのものを捨ててきた
STAGE編集部:ニューヨーク、そしてジャズというのは、大江さんにとって夢だったんですか。
夢でしたね。シンガーソングライターも大きな夢だったんですけど、その一番大きい夢が青春期に叶ったわけです。無我夢中で走りつづけて、気がついたら47歳です。その時にふと、「あ、自分にはもう一つの夢があって、その夢は同じ根っこなんだ」ってことに気がついて、やっぱり原点の夢にもう一回立ち戻りたいと思って。このタイミングを逃したらもう遅いと思って、すべてを終わらせて、ニューヨークに渡りました。
STAGE編集部:もうひとつの夢に立ち戻るのに、一番大変なことは何でしたか。
やっぱり、「捨てること」ですね。捨てるっていうと、ちょっと味気がない言い方になるのですが、全員に認めてもらって綺麗に砂をかけずに終わらせることはできない。本当に僕がやりたいという想いを、ファンの人たちに正確に伝えられたかどうかというのは、今でもわからないですね。でも、もう次に進むしかないっていう、自分なりの見極めで次のステージに行ったんです。
何を取って、何を置いていくか。大きなものを失って初めて一個の小さなフレッシュなものが手に入るのだということを、ニューヨークに渡って何年か経ってから実感しました。ジャズの学校に入って、初めてジャズの響きを感じた瞬間に、自分が10代から求めていて解けなかった謎が解けたとき、ニューヨークに来てよかったなと心から実感しましたね。

STAGE編集部:10代から求めていた、解けなかった謎とは。
僕は小さい頃からピアノを習っていたし、日本ではプロとしてポップスの世界にいたんですが、ジャズの運指というか、ジャズのボイシングがわからなかったんです。でも、ジャズの学校でクラスが一緒だった18歳のマックスは、ジャズを小さい頃からやっていて弾けるんですよ。
で、彼がF7のコードを弾いたら、明らかにポップスのボイシングと違う。「マックス、ちょっと待った!」って、とっさに彼の手を携帯で撮影したんです。家に帰ってその写真を見ながら、G7だったら1音上げてこうすればいい、C7だったらこう移動すればいいって、いろんなコードで夜明けまで夢中でやって、次の日の授業で自分の番が回ってきた時に弾いてみたら、パッとそこだけジャズになって。うれしかったですね。「あー、これジャズだ!響きができてる」って。

ショーウインドウに映った自分の顔を見た瞬間、「リンリンリン」とアラートが鳴った
STAGE編集部:いろいろなしがらみがある中で、それでも踏み出そうと思ったきっかけは何だったのでしょうか。
ジャズをやりたいという想いが、もうこれ以上ふくらまないというところまでふくらんで、「あぁ、今しかないな」っていうことが、身体と心の両方でわかる瞬間があったんです。
道を歩いていてショーウインドウに映ったんですよ、自分の顔が。その時に何か自分じゃない顔をしているというか……。底抜けな明るさとか強さとか、そういう覇気のようなものが感じられないと実感したときに、「リンリンリン」ってアラートが鳴ったんです。そのときに「あ、このタイミングだ」って思ったんです。
90年代にニューヨークに住んでいたときに、ニュースクールのジャズ校舎の前を通るたびに「いつかここでジャズを学びたいな」って思っていた時のシーンがワッと自分の中に浮かび上がって。すぐにインターネットで調べて、ジャズのデモテープを何曲か部屋で録って送ったんですよね。そしたら「approval(承認)」っていう回答がきた。で、事務所に言ったら、「千里さんがそんなにジャズをやりたいなら、行くべきだ」って。誰も止めないんですよ。「もう行くしかないじゃん」ってことになって、意外にあっさり決まりました(笑)。
それから衣装を捨てたり、CDを捨てたり、車を売り払ったり。いっぱい持っていたものを2、3ヵ月で全部引き払ったんです。残ったのは、1歳の犬と1台の電子ピアノとコムデギャルソンのスーツだけ。

STAGE編集部:日本での実績だけでなく、身の回りのものも捨てての出発だったんですね。
そう。スーツケースひとつ。持って行ったのは、ぴちゃん(犬)のおしっこシートと、コンピューターですね。でも、引っ越した屋根裏部屋に前に住んでいた人が置いていった簡易ベッドとテーブルと鍋とヤカンがあったんですよ。だから、それを全部、僕が使っていました。
知らない誰かが置いていったベッドとちっちゃい机を使っている。ニューヨークって、そういうところがあるんですよ。常に誰かが誰かにものを譲って、気がついたらまた自分のところに来ている。誰かを助けたら、自分が困っている時に別の誰かが手を差し伸べてくれる。それが毎日ある街なんです。

人生のエネルギーがどれだけ残っているのか考えたんです
STAGE編集部:47歳での決断の背景には、何があったのでしょう?
分析するといろいろあります。母の死、友達の死、愛犬の死、いろんな死が、2年ぐらいで自分の周りにいっぱいあって。喪失感もあって。自分が次の人生を考えた時に、1回しかない限りある人生、このままでいいのかって考えたんです。
このまま自分がシンガーソングライターとしてやるにしても、それ相当の覚悟がいるぞ。でも、僕はもっと人生を切り開きたい。ジャズやりたかったんじゃねーか、できるかどうかわからないけど、いつまで体力が続くかわからないけど、2~3年なら節約すればいけるんじゃないかって。
あとどのくらい、人生の歯磨き粉のチューブにトゥースペーストがあるかなって考えたときに、まだエネルギーがあるなら、そのエネルギーをもう一回自分にけしかけてみたかった。「もう武道館でライブをやってた時みたいにジャンプできないぞ」じゃなくて、「違った高さのジャンプをカッコよくできるんじゃないか」「高い跳び箱じゃなくていいから、飛べるんじゃないか」っていうような何かをもう一回やってみたいって思いがあった。
日本のポップスも、やっぱり売れる中心は10代。「ポケットの中で最初に握った手の感触、バスが小さくなって掌が点になるのを見送る、瞳でシャッターを切る……」っていう歌の世界観が中心にあるわけで、「友達の2人は2回離婚して親が亡くなって、年金が……」っていう歌詞はやっぱり詩にならないわけで。同じ場所にいるよりも、客観的にもっと違うものを違う角度で、自分が一番愛してきた曲のライティングを見つめ直したいっていう気持ちもあった。
一回、音楽の原点に戻って進む。そう思って立ち止まったときに目の前にあったのが、10代の時に脇に追いやって、いつかまたその蓋を開けようと思っていたジャズだったんです。

服は3~4年買わなかったし、高いから日本米も食べなかった
STAGE編集部:ニューヨークでの生活について、2~3年なら節約すればいけるとはいっても、学校の授業料とか、個人レッスンの費用なども必要ですよね。経済的な面での不安はなかったですか?
それまでは働いていたから、インカムとエクスペンスのバランスがとれていたけど、まったくインカムがなくなるわけです。ですから、その不安はアメリカに渡った1日目からありましたね。
春学期の授業料は、秋学期の終わりに払うんですよ。次々に数百万単位のお金が出ていくんです。NYU(ニューヨーク大学)とかマスターズクラス、大学院に行ったら2,000万円くらいかかってしまう。とてもじゃないけど、もたない。
だから、とにかく今の段階で学んできたことを形にして自分のレーベルを立ち上げて発売しようと思って。東京のブルーノートに音源を送って、「凱旋ライブをするのであれば、そちらでやりたいから、ちょっとでも響くものがあったら連絡をください」って手紙を書いた。そこから始まったんです。

STAGE編集部:実際に生活費の中でも節約をされていたんですか?
出費を1ドルでも減らそうと節約しましたね。ニュースクールの学食は高かったから食べませんでした。服は3~4年間買わなかったので、靴下に穴があきまくりでしたね。Tシャツもパンツも本当に布がなくなって破けるまで履いている。脇のところなんか、擦れて穴が開いてる。でも、適当に前に持っていたやつとかを組み合わせれば、案外オシャレなんですよ(笑)
最初はやっぱりバブルが身についているから、「何でわざわざサブウェイに乗らなきゃいけないんだ、タクシー乗ればいいじゃん」と、つい手を上げてタクシーを止めたくなる自分がいるんですよ。何で“時は金なり”なのに、夜中の大事な時間に20分もホームにいるんだって。
でも、ちょっと待った、ダメ、ダメダメダメダメって。その20分で「ダバダバダバディバディバ、ダババダバディバラーババラ、ダバレバラバリバラバ」って、ホームでずーっとジャズのリズムを練習したり、「ティヤーリヤ、ピヤリヤーワラバラリエラワラバティエラバ、パパッパビパッパーイテッィピラッティ」ってレッド・ガーランドの耳コピをしたり。それを延々、変な人みたいになってやっていました。
現実は貧しい学生なんだけども、発想は夢がある。陽転させて、今まで貧しかった自分の内面をひっくり返すという作業をやってましたね。
STAGE編集部:生活が夢でもあり、夢が生活でもある。素敵ですね。
食事もそう。日本米は食べずに、メキシコ米。で、水をたくさん入れて時間をかけて炊くと、ねちょっとした日本米みたいな感じになるになるんです。それに友達が日本から送ってくれる梅干をのせて食べていましたね。新鮮でしたね。どこまで自分ができるか。
ルームメイトのタイ人のテップと二人で節約してカレーを作って、僕がご飯を炊いたら、テップはタイ風カレーを作ります。でも、テップが文句を言うんです。「ご飯が日本風でネチャネチャし過ぎ」って。それであいつが炊くと、パサパサし過ぎ。いつもお前が炊くご飯は嫌だって言うわけ。それでお互いの部屋にプンって入っちゃう。
でもなんか心がチクチクチクチクチクチクチクってするんです。だから、しばらくすると、コンコンってテップの部屋のドアをノックして、「一緒に練習しよう」って、また仲良く練習する。やっぱり同期だから、一緒に上手くなりたいっていうのがあったのかもしれないですね。そんな、毎日が夢の日々でした。(後編へつづく)

ALBUM
Collective Scribble
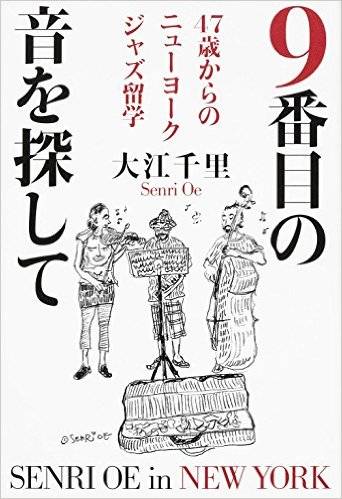
BOOK
9番目の音を探して ~47歳からのニューヨークジャズ留学~

