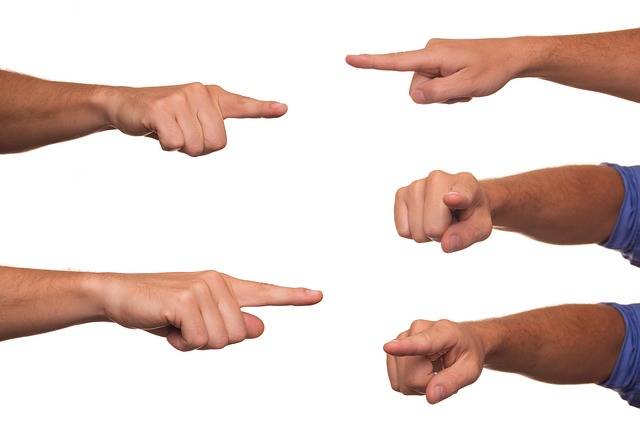2018.7.9
音声アシスタントと会話を楽しむ人々
SiriにAlexa、Googleアシスタントと、近年は音声アシスタントが注目されています。筆者も「Hey、Siri。今日の〇〇の天気は?」と尋ねることが日常風景となりました。同時に、彼らから日常生活に無用の発話を引き出そうとする「遊び」も人気。AIを搭載した音声アシスタントの役目は、どうやら情報提供や作業の遂行のみにあるわけではなさそうです。
一人暮らしの場合、帰宅して「ただいま」と言ったら「おかえり」と出迎えてくれる存在が、たとえAIでも欲しいと感じたことはないでしょうか。「賢いAI」に賢くない言葉を言わせようとしたり、わざと挑発的な言葉をかけて人間とAIを敵対させるような発話を引き出そうとする遊びを面白く感じることもあるでしょう。
しかし、人々がAIに求めるのはAIが話す・行うということだけではありません。なんとなく暇になったり気が向いた時に、ちょっとしたコミュニケーション相手になって欲しい、話を聞いてほしいと感じることだってあるのです。
ギネスブック認定、メンタルコミットロボット「パロ」
大和ハウス工業によるメンタルコミットロボット「パロ」は、音声アシスタントたちとは対極にある、仔アザラシ型のおとなしいロボット。さまざまなセンサーとAIを搭載し、人間の呼びかけや行動に反応すると共に、豊かな感情表現も行います。扱い方によって性格も変化します。日本では50箇所以上の医療機関や介護福祉施設に導入され、アメリカのFAD(食品医薬品局)に医療機器として承認されている他、2012年のギネスブックでは「世界でもっともセラピー効果があるロボット」にも認定されました。
「パロ」が導入された機関や施設では、アニマルセラピーと同様の効果を発揮していると高く評価されています。話しかけたり撫でたりすれば、それに反応して「きゅー」と鳴いたり首を傾げたり、喜んだり。自分から言葉を発することが少なかった人々が「かわいいねえ」「いいこだねえ」と話しかけるようになるだけでなく、そこに存在しているだけで入居者とスタッフの話題となって、コミュニケーションを活性化するという結果につながりました。
本物の動物は衛生上の理由や世話の問題、アレルギーの問題などで導入が難しいという場合でも、ロボットならそれらは心配ありません。「パロ」は、「ありがとう」も「こんにちは」も「愛してる」も言いませんが、人々からとても愛される存在として大切にされています。
<弱いロボット>がコミュニケーションを促進
もっとロボットらしい外見の場合も、こうしたロボット側の慎ましさは重要です。それが示唆されているのが、岡田美智男著『<弱いロボット>の思考 わたし・身体・コミュニケーション』(講談社)の<弱いロボット>たち。本書では、「何でもできる賢いAI」ではなく、どこかたどたどしいAIと人間の関係からコミュニケーションを考えています。
たとえば<トーキング・アリー>という、いびつな「目玉おやじ」のような姿のロボット。人が近づくと「あのね、えーとね」と話し出します。<トーキング・アリー>の前段階は、「オハヨウ」「アリガトウ」「アイシテル」と流暢に話すものでした。ところが、街の子供たちの反応はあまり良くない。ただ言葉を発するだけでは、「会話」にならないのです。
そこで、<トーキング・アリー>には人の目や表情を追跡する機能と、たどたどしく話す機能を搭載。社会学者グッドウィンが指摘する「聞き手性」(発話の節目で視線や姿勢を話し手に向けて「聞いてるよ」という態度を示すことなど)を考慮しました。そうすることで、<トーキング・アリー>は、どこか人間味を感じるような存在となったのです。
<トーキング・アリー>はまだ話し手ですが、こうした観点はAIが聞き手になる場合にも重要。博識なAIがどんなにしゃべっても、それだけではコミュニケーションは成立しないからです。人間が話し手の場合、AIは「聞き手性」を示さなければなりません。これからのAIには、作業遂行や情報提供といった能動性だけでなく、人間の言葉や反応を待ち「聞き手性」を発揮する受動性も求められるのです。
【参考】
パロとは?|大和ハウス工業
http://www.daiwahouse.co.jp/robot/paro/products/about.html
岡田美智男『〈弱いロボット〉の思考 わたし・身体・コミュニケーション』講談社、2017年